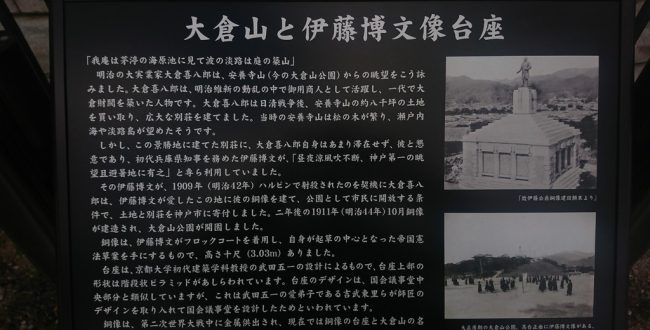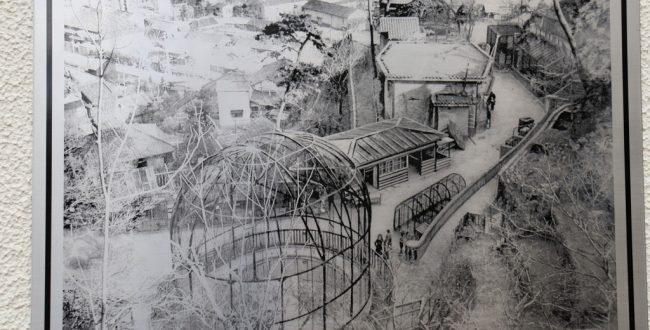眼鏡越しの風景EP50-解夏-
- 2021/8/14
- yukkoのお眼鏡

小学1年生の夏休み、母は私に1人で電車に乗る練習をさせた。その練習はなぜか夕方から始まり、母の仕事終わり、仕事先の最寄り駅で待ち合わせをしようというものだった。日中、祖父母の家に預けられていた私を、祖母がスタート地点の駅まで送ってくれた。半べそをかき、尻込みしている私に
「ここから3つ先の〇〇駅までの切符を買いなさいね」
と祖母は確かめるように言うと、そのまま来た道を振り返りもせずに帰っていた。
後からわかったことだが、祖母は心配で建物の影から様子を見守っていたらしいが、そんなことを知るよしもなく、一人券売機の前に置きざりにされた私の涙腺は崩壊寸前。心細さを振り払うように、強く握りしめた10円硬貨は、いつまでも手のひらに銅の匂いを残すこととなった。祖母が教えてくれた行先駅を忘れてしまわないよう、すぐに握りしめていた硬貨を投入口に入れ、“ここですよ!”と言わんばかりに光る赤字で「こども」と書かれたボタンを慎重に押した。気持ちとは裏腹に切符はスルーっと軽やかに受け皿へと落ちてきた。当時自動改札用の切符は裏側がチョコレート色でツルっとした手触り、出来立てでほんのり温かくいつも甘い匂いがしていた。こんな時でも「クッキーの匂いがする~!」と友達が言っていたことを思い出し、そっと鼻先にあててみる。それでもそんな少しの安心感はすぐになくなり、ひとりぼっちの現実に引き戻された。
いくつもの無機質な自動改札機が、こちらとあちらを隔てるように並び、天井高の駅構内を急ぎ足で行き交う雑踏は、あっという間に私をその一部として飲み込んだ。もう二度と家に帰れなくなるかもしれない、深い不安が押し寄せてきた。とっくに帰ってしまった祖母を追って戻ることも、母が待つ目的の駅へ進むこともできず、改札の前でついに堪えきれず、ワンワンと泣き出してしまった。買った切符をお守りのように手の中に握りしめ、汗なのか涙なのか、前髪はぐちゃぐちゃになり、ピッタリと額に貼りついていた。あまりの泣き声に、駅員さんと近くに居たおばちゃんが駆け寄り
「お母さんとはぐれたの?」
と、心配そうに声を掛けてきた。
このままでは迷子に間違われてしまうと、今出来る精一杯の“NO”は大きく首を横に振ることだった。ヒクッヒクッとすすり上げ、なかなか言葉が出ない。
「一人で電車に…ヒクっ、乗ってきなさいって…ヒッヒック、お母さんがね…ヒクッッ、駅で待ってるぅ…」
と言い、汗でシワシワになった手の中の切符を二人に見せた。なんとか途切れ途切れの言葉で、事情を察してくれた駅員さんが3つ向こうの駅に電話をし、改札に居た母に連絡を取ってくれた。一人で電車に乗る練習をしていることを知った駅員さんは、
「お母さん、がんばって一人でおいでって言ってるけど、もう少しがんばれそうかなぁ~?」
と、私の顔を覗き込み優しく微笑んだ。横で心配そうに見ていたおばちゃんが、
「おばちゃんも一緒に行こっか?」
と助け舟を出してくれ、一緒に改札を通ってくれた。駅員さんは
「ここから出る電車に乗ったらお母さんとこに着くよ」
「お母さん、3つ向こうの駅で待ってるからね~」
と言い、おばちゃんには
「すいませんが、よろしくお願いしますね」
と私を託してくれた。
知らないおばちゃんに手を繋がれる場面に違和感を感じなくもなかったが、一人で見知らぬ世界に放り出されるより、よっぽどよかった。その時は、ずいぶん長旅のように感じたが、乗車時間は10分ほど。駅に着くとおばちゃんは改札まで送ってくれ、私は母の顔を見るなり、さっきまで、この世の終わりかのようにすがりついていたおばちゃんの手をすぐに離すと、母の元へ駆け寄った。隠しきれない涙の跡を残しながらも、ここまで1人で頑張って来られたと、母にだけは思われたかったのだ。飛びついた母の肩越しに見えた、白い鳩と煉瓦造りの滝の噴水からは、水が途切れなく流れ落ちていた。
「よく、来れたね」
と母は嬉しそうに言うと、私の手に、白紙に包まれたお線香の束を握らせた。
「これ、なぁに~?」
渡されたお線香に戸惑う私に
「さぁー!地蔵盆いくよー!」
と、大きな袋の口を両手で広げ
「お菓子たくさん貰って帰ろーね!」
とおどけて見せた。
小さな手のひらからは、銅とクッキーとお線香の匂い、お地蔵さんを巡る頃には私の涙もすっかり乾き、お線香の煙揺れる路地には子どもたちの笑い声がいつまでも響いていた。
♪My Favorite Song
夏の思い出 ケツメイシ