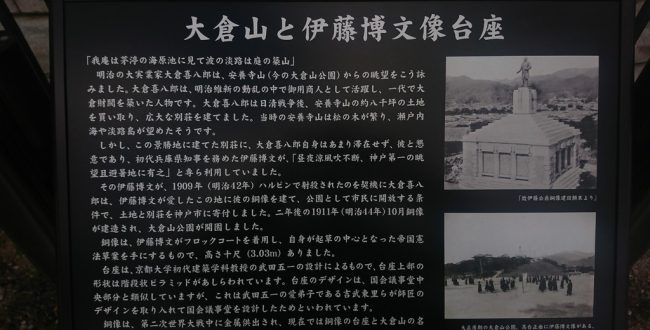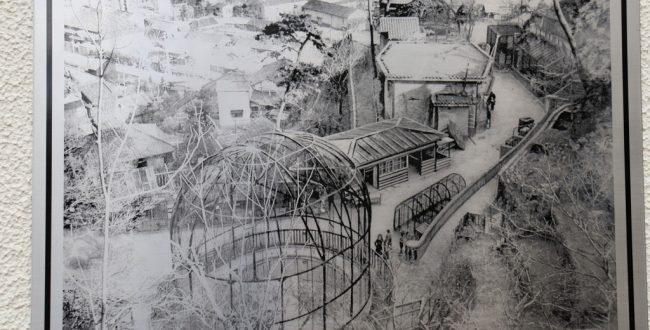眼鏡越しの風景EP38-春光-
- 2021/2/27
- yukkoのお眼鏡

子供の頃、この時期になると家に七段飾りのお雛さまが飾ってあった。
私が小学1年生の時に弟が産まれ、産後の母は自宅2階で赤ちゃんと寝ていることが多かった。ある日、学校から帰ると、玄関扉を開けてくれたのは、見知らぬおばちゃんだった。驚いて、玄関で立ち尽くしていると、おばちゃんはニコニコしながら「おかえり」と言った。
帰る家を間違ったかと、すぐに言葉が出てこず「…たっ、ただいま…」バサっと玄関に手提げ鞄を落としてしまった。おばちゃんは「お母さんたちは、お昼寝中だから、静かにね」と、口元に指を当て“シーッ”という仕草をした。どこか家の空気がいつもと違い、私は緊張した。
急いで2階に駆け上がると、ランドセルを下ろすのも忘れ、和室の襖をほんの少し開けた。スースーと母の寝息と、赤ちゃんが放つ柔らかな甘い匂い。枕元に置かれた天花粉の粉っぽさが、懐かしさと共に鼻奥をくすぐった。
今すぐにでも母を揺り起こし、「あの人誰なの~?ねぇねぇ~っ」と聞いてみたかったが、あまりにもよく眠っていたので、静かに襖を閉めた。
普段はフルタイムで仕事をする母が、平日の昼間、家に居ることがとてもうれしかった。いつもは学校から学童保育へ行き、夕方まで先生や友達と過ごすのだが、母の産休中は直接家に帰って良いことになっていた。チャイムが鳴るとすぐにランドセルを背負い、のんびりお喋りするクラスメートをよそ目に急いで教室を飛び出した。決められた通学路をすっ飛ばし、住宅街の裏道をショートカットで走り抜けてきた。なのに…帰ったら他所のおばちゃんが居るのだ。出産前は祖母の家に預けられ、夜はお迎えに来た父と2人きり、ようやく訪れた母との時間だった。
階段下から「おやつよ~!」と声がした。一段ずつゆっくりゆっくり階段を下り、食卓テーブルのいつもの席に座ると、チョコレートでコーティングされたひなあられのお皿と、牛乳が用意されていた。チョコを纏ったあられは、1袋の中に10粒有るか無いかの“あたり”。折り紙でいうと“金紙”と“銀紙”のようなレアアイテムで、めったにお目にかかれない。いつも買うあられ袋の中には少量しか入っていなかったはず、しかし今日はお皿の上全てがチョコあられなのだ。しかもホワイトチョコでコーティングされたものまである。
正体不明の謎のおばちゃんに、“あたり”だらけの入ったお皿、一体なにが起こっているのやら。戸惑いながらも、いつも母が立っている台所を、おばちゃんが自分の家のように使ってるのは嫌だなぁ…と、そこは妙に冷静だった。この人はずっとここに住むのだろうか?と不安な気持ちにもなっていた。おばちゃんは開封したあられ袋の口を輪ゴムで留め、高い戸棚の上に仕舞う。西日にキラキラ光るその中身は、全てチョコあられという夢のような袋だった。おばちゃんは時々なにかを話しかけてきたけれど、そのあとも私は戸棚の上が気になって仕方がなかった。
しばらくすると、母と弟が起きたようで、おばちゃんはお白湯やガーゼハンカチを持って2階に上がり、丸めたおむつを下のゴミ箱に捨て、階段を行ったり来たり忙しそうにしていた。私は夕方のアニメを観ながら、その動きを横目で追ってはいたが、知らんぷりをしていた。
その後もおばちゃんは台所でごはんを作り、洗濯物を畳みと、手際よく家事をこなしていった。外が暗くなる頃、母となにやらお喋りをし、「それでは、失礼します」とエプロンを手早く畳み、手提げカバンに仕舞うと「また明日ね」と私に声をかけ、帰っていった。入れ替わりに父が帰って来て、用意されたごはんを2人で食べた。
「美味しい…」
それから、土日を除く毎日学校から帰ると「おかえり」と、おばちゃんは私を迎えてくれた。少しこの状況に慣れた頃、生意気にもチョコあられのおかわりを要求してみた。「たくさん食べたら、ごはんが食べれなくなるからね~」と、そこは母と言うことが同じだった。“チョコあられは母が私に買ったもの、高いところに仕舞い意地悪をしている”、私に内緒でこっそり食べているのだろうとさえ思っていた。
彼女が2階に行っている隙に何度か椅子に乗り、チョコあられ奪還を試みた。背伸びをして手を伸ばしても、あと少しのところで届かない。あちらもなかなかで毎回戸棚の上の、少し奥に仕舞ってあるのだ。
突然やって来た意地悪なおばちゃん、おやつを貰えない可哀想な私、実の母は床に伏せっている…いつの間にかシンデレラ風の悲劇のストーリーに仕立て上げ、ずいぶん想像力豊かな子供だ。
結局、おばちゃんの正体はその後もわからず、何十年もしてから母に尋ねた
「弟が産まれた頃に来ていたおばちゃんって…あれ誰だったの?」
「あの当時、お父さんの会社で、産後にヘルパーさんを頼める制度があったの、いわゆる家政婦さんね」
今思えば、おばちゃんは母の申し伝えをきちんと守り、産後の母に代わって私たち家族のお世話をして下さる救世主だったのだ。
「“おばちゃん”って、失礼ね~。あのヘルパーさん、その頃まだ20代よ」
そう言うと、母は懐かしそうに笑っていた。
子供の想像力と悲劇のヒロインフィルター恐るべし。
♪My Favorite Song
誕生 中島みゆき